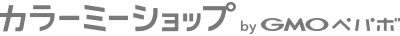第三話:『ポッペンとプッピンと真夜中の庭』
「なんだかいいにおい」プッピンはさっきから窓の外に顔を出してうっとりしています。「なんのにおいだろう」ポッペンも目を閉じてにおってみました。外といっても夜のことです。いっせいに咲き始めたチェリーの花もジャンヌ・ダルクというすごい名の白いクロッカスもブルーのムスカリも、家の外の小さな庭の住人たちはみんな今は眠っているはずなのに、なんともいいにおいがするのです。それは植物たちがいっせいに芽吹いて、すうすうと呼吸をはじめたとき特有のいい香りだろうか__と、めずらしくポッピンが詩人めいたことを考えていると
「シーッ、しずかに」という声がきこえたのでビックリして目をあけました。
「プッピン、今なんか言った?」
「それはこっちのせりふよ」
「シッ、しずかに」
また声がして、ふたりは黙りました。
「いま、もうちょっとで目覚めるところなんですから」
「そう、やっと」
「そう、百年の眠りからね」
「百年だって?」
「だってあたしたちがやってきたときにはもう……」
「彼女は夢の世界に生きていたんだ」
「でも、もうちがう」
「彼女は目を覚まそうとしています」
「もうすぐだ」「もうすぐだ…」
ひとりではありません、三人か五人、いやもっといるかもしれません。ワイワイ、ザワザワ、奇妙なささやき声が庭から聞こえてくるのです。ポッピントプッピンは固唾をのんで、庭の中を目を皿のようにしてみましたが、部屋の明かりにうっすらと照らされた庭にはもちろん人影などどこにも見あたりませんでした。
ただ翌朝になってふたりはようやく気づいたのです、庭のかたすみにいつからか植わっていたバラの、固いつぼみのままルビーの宝石のように凍りついていた花がわずかにほころんで、それはいい匂いをえんりょがちに漂わせていたのを。
庭は今、いろんな花がいっせいに先そろって風に揺れています。
(おしまい)

 おはなしtopにもどる
おはなしtopにもどる  プチコパンtopにもどる
プチコパンtopにもどる 

 動物
動物 食べ物
食べ物 人
人 お花・葉
お花・葉 虫
虫 自然・天気
自然・天気 ハート
ハート マリン
マリン きのこ
きのこ 小鳥
小鳥 のりもの
のりもの 昭和レトロ
昭和レトロ ハロウィン
ハロウィン クリスマス
クリスマス フランスのボタン
フランスのボタン ハンドメイドの記録
ハンドメイドの記録 プチコパンのこと
プチコパンのこと ポッペンとプッピン
ポッペンとプッピン works
works 作り方いろいろ
作り方いろいろ