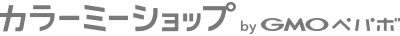第二十四話:『六月の夜の発動機』
雨がふりそうで、ふらない。もう少しで虹が出そうなのに、出ない。すべてそんな空のように曖昧な日々がつづいて、フェルト製の ネズミ、スマッフィーはすっかり湿気てしまいました。
ええ、フェルトがです。ほんの表面の問題であるはずなのに
「ぼくなんだか重たくなってきちゃった。まるで湿気たビスケットみたいに」
天才手品師のスマッフィーも6月の海に囲まれたジャパン・アイランドの 湿気にやられて元気がありません。
「ええと、湿気たビスケットはどうすればいいんだっけ?」とポッペン。
「鉄板に並べて、オーブンレンジでチンすれば、もとのパリパリッに戻るよ」と 確信に満ちてプッピン。
「ぼくをレンジでチンしないで!」スマッフィーは悲鳴をあげました。
「こんな話があります」ポッペンはおもむろに言いました。
「好きなものを思い出してください。よくよく思い出して、 ほんとうに好きなものを。人でも何でもいいから。 そうすれば、心臓のポンプが発動して、カッカッて全体に火が行き渡って、 内側からカラリと乾いてくるというしくみです」
「誰に教わったの?」みなが叫ぶのに、ポッペンは平然と 取り澄まして答えます「ワニの詩人に」。
なるほど、高温多湿の国でいつでもカラリと乾きながら、 なおかつワニ氏の心が燃えているのは、そのような発動機を 体内でたえず作動させているからだ、と珍しくポッペンが力説 するのを聞いているだけで、ほら、なんだかカッカッて、心臓の音が 聞こえてくるようではありませんか?
「バグダッドの四ツ辻でたべたイワシとトマトのサンドウィッチ。レモンがかかった。 そのイワシを揚げていた男の子の銀の三日月の耳飾り……黒ビロオドに 満天の星を縫いつけたサーカステントの垂れ幕…それから…」
好きなものをスマッフィーは次々に思い出しています。
「ぼくが旅行中に寝ていた小さなトランク。あの中にはピンポンみたいに 小さいのに重たい水晶玉も入っていて、一晩中チリチリと光っていた…そうなんだ、 今こうしてお話していることもみんな、あの水晶玉にはみんな映っていたん だ…そして」
しだいにスマッフィーの心臓がカタカタと高鳴ってきました。スマッフィーの体は だんだんと暖かく熱くなってきました。夕方なのか、もう夜になったのかも わかりません。明日は少し晴れるでしょうか? 星はまだ出ていません。
しかし草のいい匂いがします。心臓の発動機が廻転するまで、あと少しです。
どれ、ワニの詩人にならって、ここらで私たちも試してみるとしましょうか……
(おしまい)

 おはなしtopにもどる
おはなしtopにもどる  プチコパンtopにもどる
プチコパンtopにもどる 

 動物
動物 食べ物
食べ物 人
人 お花・葉
お花・葉 虫
虫 自然・天気
自然・天気 ハート
ハート マリン
マリン きのこ
きのこ 小鳥
小鳥 のりもの
のりもの 昭和レトロ
昭和レトロ ハロウィン
ハロウィン クリスマス
クリスマス フランスのボタン
フランスのボタン ハンドメイドの記録
ハンドメイドの記録 プチコパンのこと
プチコパンのこと ポッペンとプッピン
ポッペンとプッピン works
works 作り方いろいろ
作り方いろいろ